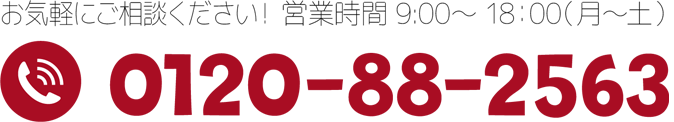【動画】畳の歴史
みなさんご存知の畳は日本で生まれました。
そんな日本の伝統文化である畳について簡単にご紹介しましょう!
奈良時代の畳
存在する古い畳は奈良時代の畳です。
あの有名な【古事記】にも畳の話は登場します。
御床畳(ゴショウノタタミ)という木でできた台の上に置かれたものが、
奈良東大寺の正倉院に保管されています。
当時は寝るときのベッドのように使用していました。
794年くらいから畳があったのですが、ゴザのような扱いでしたので
当時はまだ畳床はありませんでした。
今でいうフローリングに置くという使い方で、
使う人の身分によって畳の厚さやへりの柄・色を変えていた
というの話は知っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その後、鎌倉時代から室町時代にかけ、書院造が生まれて、
やっと部屋全体に畳を敷くようになりました。
ようやく庶民にも
そして、桃山時代から江戸時代に数奇屋造や茶道が発展して普及し、
徐々に街の家にも畳が敷かれるようになりました。
部屋全体に敷き詰められるようになったことにより正座がされるようになります。
引越しの時は一緒に持ち運んでいたそうです。
そのために、畳は家具などのようにとても大切にされてました。
江戸時代後期にはようやく庶民の家にも使用されるようになっていきます。
畳離れが加速
椅子やソファーの生活へと変わりました。その結果、フローリングが広く普及しました。
また、コスト削減のために和室の部屋が作られないことが増えてきました。
平成に入ると
テレビの番組やCMでも畳が取り上げられることが多くなり
日本の良さというものが再認識されてきているのではないでしょうか。
畳の歴史ってとても長いんですよね!
最後までお読み頂きありがとうございました。
====================================
畳の保田
神戸市西区高塚台3丁目2−4
℡0120−88−2563
保田貴政
[営業時間]9時〜18時
[定休日]日・祝
メール:info@tatami-yasuda.com(24時間受付中)
お気軽にお問い合わせください!!
======================================